八潮市陥没事故を教訓として町田市の下水道行政を考える
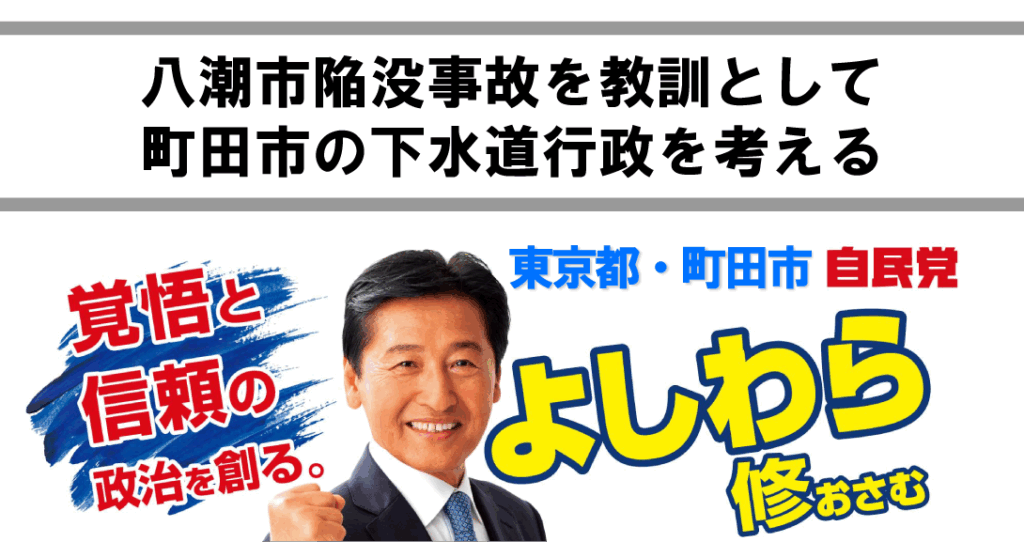
2025年1月28日、埼玉県八潮市で県道の道路が突然陥没し、走行中のトラックがその穴に転落するという痛ましい事故が発生しました。運転手の方は行方不明となっていましたが、本日、下流約30メートルの下水道管内に沈んでいたキャビンの中から引き上げられ、死亡が確認されております。突然の不慮の事故で命を落とされた運転手の方のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。
今回の八潮市における道路陥没事故は、我が国が抱えるインフラ老朽化の現実と、その深刻な危険性をまざまざと突きつけました。二度と同様の事故が繰り返されないよう抜本的な対策が必要です。とりわけ下水道という、市民の暮らしの基盤を支える社会資本に対しては、予防的・計画的な管理への転換が急務です。
国土交通省はこの事故を受け、全国の下水道管理者に対して、直径2メートル以上の大規模な下水道管路に関する緊急点検を指示しました。町田市では対象となる施設はありませんでしたが、市として自主的に58キロメートル分の管渠について緊急点検を実施。その結果、現時点で緊急対応が必要な異常は確認されなかったと報告されています。
とはいえ、それで安心しきれる状況ではありません。町田市内では、経過年数30年以上を超える下水道管が着実に増えており、2030年には全体の約7割が耐用年数を超えると見込まれています。いま私たちに問われているのは、単なる施設の延命措置ではなく、「将来を見据えた再構築」にどう取り組むかということです。
特に町田市の場合、東京都の流域下水道に依存せず、市が独自に管理・運営を行っている町田市単独の「公共下水道」です。多摩地域の自治体のほとんどが東京都の豊富な財政力と技術力に支えられているのに対し、町田市は限られた人材と財源の中で、自前の施設を維持・更新していかなければなりません。この構造的な違いが、今後の下水道政策をより慎重かつ戦略的に考えていく必要性を、いっそう強くしています。
まず必要なのは、予防保全を前提とした下水道インフラ管理の制度化です。現行の法定点検制度では、リスクの高い老朽管の全容を把握するには不十分です。点検対象の拡大と、全国一律のインフラ台帳の導入、点検記録の義務化が国として取り組むべき課題だと考えます。町田市においても、独自にストックマネジメント計画に基づいた定期点検や補修を進めていますが、これをさらに強化すると同時に、市民に対して透明性のある情報公開を行っていく必要があります。
また、こうした取り組みを現実のものとするためには、財政・人材の両面での支援が不可欠です。私は、特に中核市や中小自治体への国による技術支援と財政支援の抜本的な拡充を強く求めていきます。ICTやAIを活用した点検機器の導入支援、技術職員の育成、そして地域間での技術共有が可能となるようなプラットフォームの整備が必要であると考えます。
町田市ではすでに国のB-DASHプロジェクトにも参画し、AIによる下水処理の自動制御実証を進めています。こうした先端技術の活用を、点検・維持管理の現場にも広げていくことで、人手不足や財政的制約にも対応しつつ、効率的で持続可能な下水道運営が実現できるのではないでしょうか。
下水道は、日常の中で「見えない」からこそ、その危機にも気づきにくいインフラです。だからこそ、今回のような事故を一過性の出来事にせず、私たち自身のまちである町田から「見える化」し、持続可能な下水道管理モデルを築いていく必要があると考えています。
#よしわら修 #町田市 #下水道

