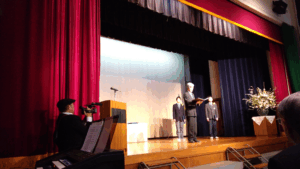自治体DXとAI活用の一考察

先日、一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム(OGC)が主催するシンポジウム「自治体DX待ったなし!デジタル活用のシナリオ」が東京・平河町の全国町村会館で開催されました。基調講演では、自民党デジタル社会推進本部長の平井卓也衆議院議員が登壇し、日本のデジタル政策の課題と未来についてのお話をいただきました。その他にもデジタル庁や総務省、自治体関係者が登壇し、日本の自治体DXの現状と課題、今後の展望について活発な議論が行われたところです。
現在、日本の自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)は待ったなしの状況にあります。いま民間では当たり前となったAiを含めたデジタル技術は急速にの進展しており、それを活かせるかどうかが、地域市民の利便性の向上や生活の質、ひいては自治体の未来に大きく左右します。
シンポジウムの内容を基に、自治体DXのあるべき姿、AIの活用法について私なりの考えを整理します。ただし、自治体DXは技術革新の進捗にともに同時並行的に進んでいる施策であることと、私自身がデジタル関連の専門家ではありませんので、あくまで限定的な視点であることはご承知おきください。
なぜ自治体DXが必要なのか?
自治体DXとは、古くはコピー機の導入や、2000年前後頃から本格導入されたパソコンやオンライン化のときと同じような、"行政内部の効率化"を推進る単なる”ITシステム”の導入ではなく、行政のあり方そのものを変革するプロセスです。これまでの行政手続きは、紙ベースでの運用や対面対応が中心でしたが、デジタル技術を活用することで手続きの簡素化や迅速化、市民サービスの向上、コスト削減、労働生産性の向上が期待できます。
特にコロナ禍以降、各自治体ではネットを活用した申請手続きやオンライン会議の導入が進み、DXの必要性がより鮮明になりました。住民票はじめとした各種証明書類のオンライン請求や補助金の電子申請といった施策が多くの自治体などで実施されていることはご存じだと思います。また、一部ではチャットボットを活用した問い合わせ対応の自動化も始まっています。こうした取り組みにより、行政内の事務処理が効率化されただけではなく、市民にとっても利便性が大きく向上したと評価されています。
また、政府が進める「デジタル田園都市国家構想」も、自治体DXを後押しする施策のひとつです。この構想は、デジタル技術を活用して地方の課題解決と価値創造を図ることを目的としています。都市部と地方のデジタル格差を縮小し、全国どこでも均質な行政サービスを提供できるようにするための取り組みが求められています。
東京都の取り組み
東京都では、事務処理のデジタル化を含めたDXの推進を進めています。その一環として、「庁舎DX推進ガイドブック&事例集」を作成し、全国の自治体と共有することでDX推進の標準化を図っています。このガイドブックには、市民サービスを改善する窓口DXの取り組み、災害に備えた電源・通信の多重化、庁内システムのクラウド化、Wi-Fiネットワークの最適化など、自治体DXを加速するための具体的な戦略が示されています。こうした取り組みは、東京都内のみならず全国の自治体DX推進の指針となっています。
町田市の取り組み
町田市では、「町田市デジタル化総合戦略2024」を策定し、バーチャル市役所の実現に向けたDXの推進を掲げています。生成AIなどの最新技術の導入を進めることで、新たな価値創出を目指しており、メタバースを活用した広報活動や、クラウドサービスの導入による業務効率化にも取り組んでいます。また、「Tokyo区市町村DXアワード」において行政サービス部門の優秀賞を受賞するなど、その取り組みは高く評価されています。
こうした東京都や町田市の事例につても、まだまだ充分ではないことは承知していますが、自治体DXは確実に進展しており、それぞれの自治体が独自の施策を展開しながら、より利便性の高い行政サービスの提供を目指しており、今後の技術進展によりさらなる利便性をもたらすことは間違いないはずです。
まずは標準化をすすめるべき
自治体DXを推進するうえで、各自治体が独自のシステムや手続きを構築するだけではなく、庁内はもとより全国的な標準化を進めることが重要だと考えます。データのフォーマットやクラウドサービスの利用基準を統一することで、データ処理が効率的に行えることができます。
しかし、現在のところ、庁内や自治体ごとのシステムや手続きが統一されておらず、標準化の遅れが大きな課題となっています。その結果、データ連携がスムーズに行えず、業務の効率化が妨げられています。また、異なるベンダーのシステムが導入されていることで、開発や運用のコストが膨らみ、互換性の問題からシステムの維持・更新が困難になるケースも少なくありません。こうした課題を解決するためには、各自治体が共通の基準をもとにデジタル基盤を整備し、より効率的で持続可能な行政サービスを実現することが求められます。
こうした課題を解決するためには、国が主導する形で統一的なシステムの基盤を整え、全国の自治体がスムーズに導入できる仕組みを構築することが求められます。東京都の取り組みのように、全国の自治体が活用できるガイドラインや事例集を共有し、効率的なDX推進を図ることが必要です。
AI活用の可能性
自治体DXを進めるうえで、現在急速に技術進化しているAIの活用は欠かせません。AIの活用によりこれまで以上に行政手続きの自動化を進めることで、庁内業務の効率や、市民の利便性を高めることができます。また、民間企業と同様に、問い合わせ対応にチャットボットを導入すれば、24時間365日対応が可能となり、窓口業務の負担も軽減できます。さらには、将来的にはAIを活用したデータ分析により、市民ニーズに即した施策がスピード感をもって進められるはずです。
ただし、これらの施策を進める際には、自治体ごとの特性やデジタルデバイド対応や市民のITリテラシーも考慮する必要があり、単に先進技術を導入するだけでは十分でないことも承知しています。
デジタル人材の育成と職員活用の課題
AIを活用するためには、自治体職員もデジタルリテラシーの向上が不可欠です。現在、多くの自治体では職員のITスキル不足が課題となっています。これを改善するためには、定期的なデジタル研修を実施し、職員が実際にデジタルツールを活用できる環境を整備することが求められます。また、民間企業との連携を強化し、実践的なスキル向上を図る取り組みも重要です。
加えて、DXが進むことで職員の業務量が大幅に削減される可能性もあります。こうした際に、職員の削減も一つでしょうが、人でなければ対応ができない地域の課題解決や、これまで人材不足で対応することが難しかった市民一人一人に対するサービスの充実に向けた対応など、自治体の状況に応じた新たな仕組みを考えることも重要です。
セキュリティ対策の強化が最重要課題
自治体が扱うデータは非常に機密性が高いため、セキュリティ対策は最も重要です。データの暗号化やアクセス管理の徹底、クラウド利用に関するガイドラインの策定、専門家によるセキュリティ監査の実施などを推進する必要があります。デジタル化が進む中で、市民の個人情報を確実に保護し信頼得ることが、DX推進につながると思います。
私が目指す自治体DXの未来
これまで述べてきたように、自治体DXの成功には、最新の技術を取り入れるだけでなく、デジタル人材の育成やセキュリティ強化を同時に進めることが不可欠です。また、効率化の結果生じる余剰職員の活用についても、今後の自治体運営における大きなテーマとなると思います。
市民と行政がデジタルでつながる新しい地域コミュニティの形成は、新たな時代の地域づくりには必要な施策に不可欠だと考えます。
【参考・引用文献】