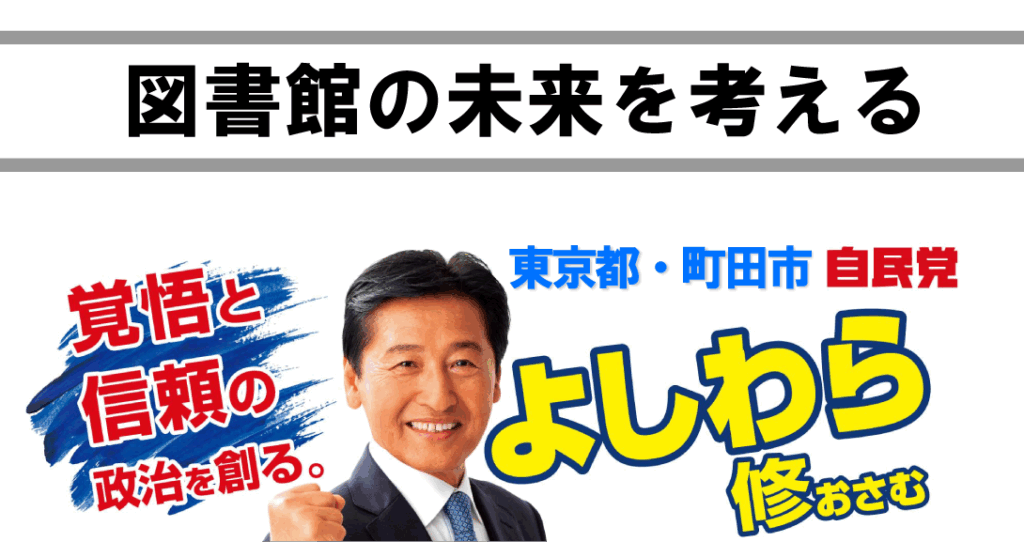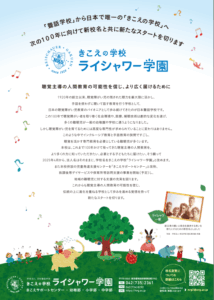「知のプラットフォーム」図書館の未来を考える
【町田市立図書館、リニューアル完了】
2025年3月25日より、町田市立図書館は新たな図書館情報システムを導入し、サービスを再開しています。
あわせてLINEとの連携も開始され、資料の検索・予約・通知受け取りがより便利になっています。
私も行政資料の閲覧で年に何度か利用していますが、学習支援機能のさらなる充実であったり、地域交流の拠点としての機能強化など、図書館が「知のプラットフォーム」として常に進化していくことが必要だと思います。私なりの図書館行政に関する展望を整理したいと思います。
【図書館は地域課題の解決拠点へ】
これまでの「本を借りる場所」から、図書館は地域の交流・学習・相談の拠点、いわば「知のプラットフォーム」へと役割を広げるべきと考えています。中央図書館だけでなく、各地域の図書館においても、地域コミュニティの拠点、リカレント教育の支援、さらには子どもや高齢者の居場所づくりなど、新しい公共施設としての役割が必要だと考えます。
【市民参加による図書館経営】
市民の意見やアイデアを取り入れた運営体制に移行するべきです。行政主導ではなく、利用者とともに考える図書館。こうした「住民協働型」のマネジメントが、信頼と利用率の向上、さらには、地域での新たな役割や課題解決につながるのと思います。図書館は「まちづくりのパートナー」であるという認識を広めていくべきです。
【ICTと図書館サービスの融合】
今回はLINEとの連携によるカードレスへとサービスが拡充していますが、電子書籍の更なる導入、ウェブ予約や検索機能の強化など、ICTの活用はとても大切です。古い行政資料を電子化することももちろんですが、自由民権資料館や版画美術館などに所蔵する資料の電子化を進めて、図書館アカウントで閲覧できるような仕組みづくりも必要です。
こうしたICT化にあわせて、高齢者や障がい者を含めたすべての人に使いやすいデザインも重要です。
【図書館の役割を再定義する】
防災拠点、行政情報の発信基地、学び直しの支援機関など、図書館が担う新たな役割について市民協同でアイデアを出していくべきです。それが、"地域の知的インフラ"としてなることが、私の考える図書館の未来像です。
【おわりに】
図書館の進化は、地域に暮らす人々の学びや交流を支え、まちの未来を形づくる基盤となります。今後も時代の変化に対応しながら、市民とともに創る図書館を考えていきたいと思います。